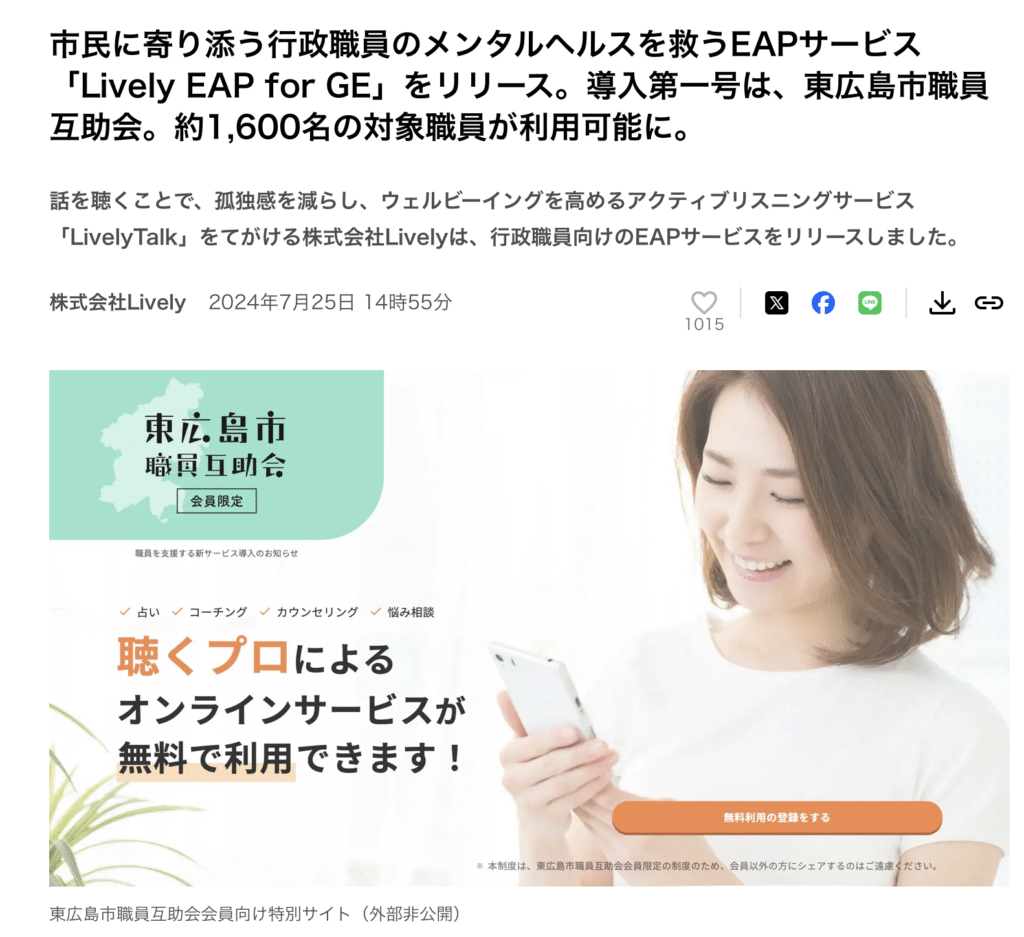はじめに
登壇スタートアップはこれまでに113社※、累計500件以上のConnect!(コネクト)実績を誇る共創プラットフォーム、Monthly Pitch「7minutes」。 2021年のスタート以来、全国31の自治体が参加し、スタートアップ1社あたり平均4.6自治体とつながることができる、継続的な共創・連携の場として高く評価されています。(※2025年5月時点)
今回はその成果の一例として、この「Connect!」をきっかけに導入に至った、株式会社Lively × 東広島市による2024年の共創事例をご紹介します。
Monthly Pitch「7minutes」とは?
地域のキーマンである自治体職員とスタートアップの出会いが、大きな社会的インパクトを生むと考え、2021年に立ち上げられた共創イベントです。 独自の「Connect! or Nice!」方式を採用し、全国の熱意ある自治体職員(通称:スタメン47)とスタートアップをつなぐマッチングの場として実績を積み上げています。
本企画は、フォーアイディールジャパン株式会社と一般社団法人スマートシティ・インスティテュート(SCI-Japan)の共催により、開始当初から完全ボランタリーで運営されています。
Livelyと東広島市 ─ 共創をかたちにした人と組織
【株式会社Livelyについて】

「ひとりひとりが自分らしく生きられる社会をつくる」をミッションに、アクティブリスニング(傾聴・共感・深掘り)を軸としたオンラインサービス「LivelyTalk」を展開。“話を聴く力”に特化した人材を育成し、個人向けの傾聴プラットフォームをはじめ、企業・自治体向けの研修・EAP(従業員支援)プログラムも提供している。 カウンセリングのような敷居の高さを取り払い、「もっと気軽に、誰でも話を聴いてもらえる社会」の実現を目指している。 今回の東広島市との取り組みは、同社にとって初の自治体導入事例となった。
◯ 岡 えり 氏
株式会社Lively 代表取締役社長
作業療法士として精神科病院や在宅リハビリに従事した後、3児の育児と仕事の両立が困難となり退職。専業主婦を経て、2020年にLivelyを創業。「聴く力」を活かして在宅でも働ける仕組みをつくりたいという想いから、誰もが安心して話せるプラットフォームを立ち上げた。
【東広島市について】

人口約19万人。大学が集積する学園都市であり、近年は半導体産業の誘致にも注力している。「Town & Gown構想」のもと、地域の多様なステークホルダーとの連携に積極的な自治体である。
◯ 栗栖 真一氏
経営戦略担当部長
本取り組みを牽引したキーパーソン。Monthly Pitch「7minutes」にはスタメン47の一員として登壇中。 地元・東広島市役所に入庁後、国際交流・政策調整・観光・保育などを担当し、農業振興係長、人事係長、職員課長を経て現職に就任。総合計画や大学との連携、広報などを所管。 「人はなぜ行動するのか」という大学時代の学びを原点に、好奇心とワクワク感を大切にしながら新たな取り組みに挑んでいる。
◯ 村上 雅之氏
総務部職員課長
本取り組みにうまく巻き込まれた実行役。栗栖部長の元部下。路頭に迷う寸前で東広島市役所に拾ってもらい勝手に恩義を感じている。入庁後、林業振興、障がい者福祉、職員給与、財政などを担当し、財政第2係長、人事係長、行政経営係長を経て現職に就任。組織・人事、働き方改革を所管。
「まずは話してみないと分からない」から始まった共創
2024年3月に開催された第24回Monthly Pitch「7minutes」に登壇したLivelyは、「“聴く”で社会の孤独・孤立を減らす」をテーマにピッチを実施。
① 市民向けサービス(アクティブリスニングの個人利用)
② 自治体職員向けプログラム(メンタルヘルス研修・EAP) の2軸を提案し、4自治体からのConnect! (マッチング機会)を獲得しました。
その後、各自治体とのオンラインミーティングを経て、具体的な導入に向けて動き出したのが東広島市でした。
本取り組みを主導したのは、毎回「市の課題とスタートアップをどうマッチさせるか」を意識して参加している栗栖氏。 「まずは話してみないと分からない」という柔軟な姿勢でLivelyとの対話を始め、適切な関係部署へとつなぎました。
一方、Lively側は自治体導入が初めてだったことから、複数の提案パターンを準備し、相手のニーズを丁寧にヒアリング。 当初は市民向け・子育て支援を想定していましたが、打ち合わせを重ねるなかで「職員のメンタルヘルス」へのニーズが顕在化し、そこから方向性を転換。共創の土台が整っていきました。
導入までのプロセスと工夫 ─ 柔軟さと対話の積み重ねにより、わずか4ヶ月で導入を実現
導入を強く後押ししたのは、同市職員課 課長の村上 雅之氏でした。自身の“猛烈に働いてきた”経験を踏まえ、「今の職員には、心身の健康や生活の充実も含めた“ウェルビーイング”を大切にしながら働いてほしい。」──そんな強い思いが、プロジェクト推進の原動力となりました。
費用面では、職員互助会の予算を活用。互助会は、自治体職員の福利厚生を目的とした相互扶助組織であり、今回の取り組みにも高い親和性がありました。通常の行政予算では実現が難しい施策に対しても、柔軟かつスピーディに対応できる点が、実行の鍵となりました。
成果と広がり ─ 押しつけない、“選ばれる”仕組みがじわり浸透
Livelyのサービスは、「職員が“自ら選べる”」ことを大切にしており、導入直後の急拡大ではなく、自然な認知と定着を目指すスタイル。 若手職員や新卒職員向けの案内にも活用され、徐々に浸透が進んでいます。
利用促進の工夫としては、約1,600名の職員に向けたチラシ配布、市内掲示板でのセルフケアコラムの発信などを実施。職員が「気軽にアクセスできる」導線を意識し、Livelyと市が一体となって取り組んでいます。
現在は、東広島市での導入をきっかけに、神奈川県をはじめとする他自治体や教育機関とも連携が進行中。教職員向けのメンタルヘルス支援など、新たな展開が始まっています。
こうした広がりのきっかけとなったのが、Monthly Pitch「7minutes」への登壇でした。
岡氏は、「Monthly Pitch『7minutes』は、熱量があれば相手に伝わる場。何度でもチャレンジできるし、行政と本音で話せるのが大きな魅力です」とコメントしています。
まとめ ─ 共創の鍵は『つながり』と『対話』にあり
共創を実現する鍵は、人と人とのつながり、そして相手の声に耳を傾ける対話の姿勢にあります。
全国のスタートアップと自治体職員が、オンラインを通じて7分間のピッチをもとに、効率的かつ効果的に「つながる」ことができる──それが、Monthly Pitch「7minutes」の最大の特徴です。
スタートアップの心得としては、自治体ごとに異なる状況や仕組み、ニーズを理解し、「聞く」姿勢を忘れずに、社会課題を地域課題へと丁寧に落とし込むことが大切です。
一方、自治体は今回の事例のように「まずは話してみないと分からない」という姿勢を持ち、将来を見据えた視点でスタートアップからの情報共有が未来につながることを理解する必要があります。また、役所内にとどまらず、地域企業や学校、病院など、地域全体とのつながりを意識することも重要です。
こうした『対話』の積み重ねが、共創の原動力となります。
今回の事例は、Livelyの柔軟な対応力と、東広島市のスタートアップとの積極的な連携姿勢が合致し、新しい社会課題へのアプローチが生まれた好例となりました。
予算や運用、認知といったハードルはありますが、スタートアップと自治体が共に考え、育てていく姿勢があれば乗り越えられます。
だからこそ、Monthly Pitch「7minutes」をスタートアップと自治体の双方にぜひ活用してほしいと思います。
Monthly Pitch「7minutes」は、出会いの“起点”となる場所です。
これからも、Connect! の“その先”を見届けていきます。